
脳性小児麻痺という障がいをもって生まれて
私は、脳性小児麻痺という障がいを持って生まれてきました。原因は胎児期の脳への何らかの障害とされていますが、正確な理由ははっきりしていないそうです。
生後半年くらい経った頃、母方の祖母が首のすわりの遅さに気付き、両親が各地の病院を訪ねてまわった末に、脳性小児麻痺と診断されました。
手足には麻痺がありましたが、歩いたり文字を書いたり絵を描いたりと、自分なりの工夫をしながらできることを増やしていきました。ただ、言語障がいのため、初対面の方には思うように話が伝わらないことも多くありました。
知能指数の診断結果、知能には問題がないとの事でしたが、小学校への進学に際しては「特殊学級」を勧められました。けれども、おふくろが教育委員会に何度も訴えてくれたことで、普通学級に通うことができました。
今から50年以上も前、障がい者への理解が今ほど広まっていなかった時代に「普通学級へ」とこだわった、おふくろの思いには深い覚悟があったのだと今では思います。

おふくろの覚悟
入学した小学校には、障がいを持つ友達はひとりもいませんでした。「なぜ自分だけが障がいを持っているのか」「みんなのように自由に動けたら…」そんな悩みが、子どもながらに心を占めていた日々。
そんな私の姿に見かねた、おふくろに連れられて、ある重度障がい児施設を見学に行きました。そこにいた子どもたちは寝たきりで、話すこともできませんでした。でも、私に向けて綺麗な瞳で笑いかけてくれたのです。まるで「来てくれてありがとう」と言うように。
重い障がい、軽い障がいという考え方が好きではありません。でも、その日出会った彼らの笑顔が、私の中で大切な心の拠り所になったのは間違いありません。
いじめも経験しました。ただ、その時代のいじめは今のような陰湿なものとは異なり、「やめろよ」と言って手を差し伸べてくれる友達も必ずいてくれました。時には、いじめた本人が涙ながらに理由を話してくれたこともありました。
運動会では、リレーの選手に私が選ばれると保護者から「走らせないでほしい」と電話が来ることもありました。私が走ると最下位になってしまうからです。
それでも「僕が挽回するから一緒に走ろう」と言ってくれた仲間がいて、みんなでゴールまで走り切ったことは、今も鮮やかに覚えています。
心配性のおふくろのこと、私を特殊学校に入れれば安心だっただろうに。おふくろは、おそらく運動会や学芸会、遠足などの様々な壁を通して、「社会に出たときに壁にぶつかっても、どう乗り越えていくか」を私に体験させてくれていたのだと思います。
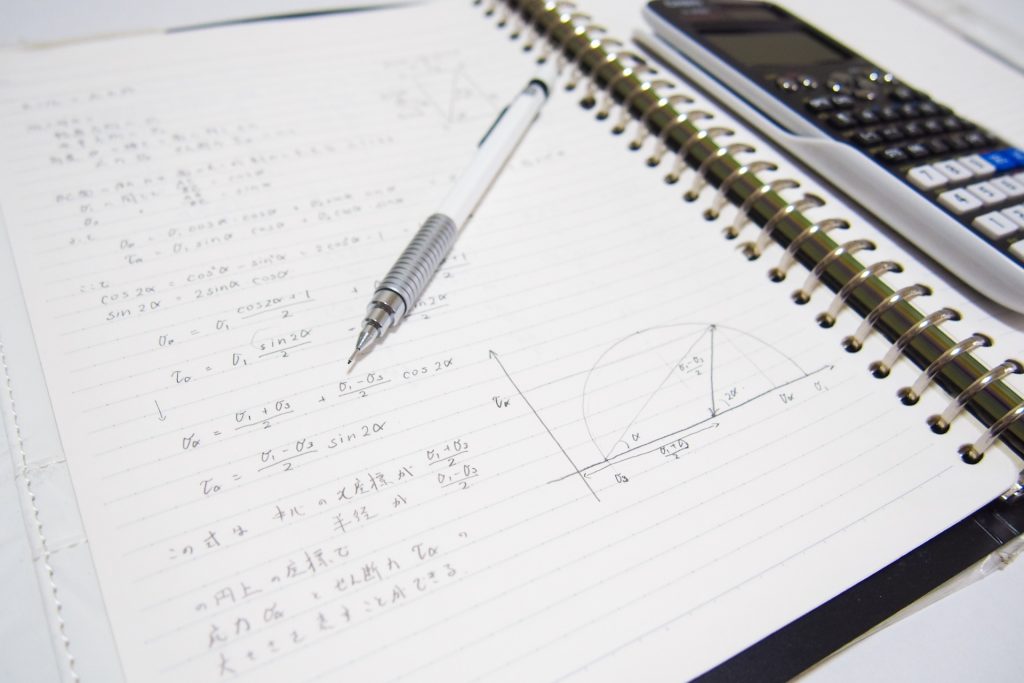
懸命に頑張ってさえいれば
最寄り駅からバスで約25分。新築の家々が並ぶニュータウンを抜け、小高い丘陵の坂道を上った先に、私たちの大学はありました。スクールバスはいつも満員でしたが、新緑に包まれた車窓の景色が爽やかで、心を落ち着かせてくれました。
私は、数学・物理・コンピューターサイエンスを中心とした学科に進み、とくに解析学を集中的に学びました。
大学には「輪講」と呼ばれる授業があり、解析学の名著を節ごとに読み解き、順番に発表するというものです。初めて自分に発表の順番が回ってきた時、正直不安でいっぱいでした。黒板に書く文字も下手でしたし、言語障がいもあったため、内容がうまく伝わるか心配でした。
それでも無我夢中で話し切ったとき、「説明が丁寧で分かりやすかったよ」と言ってくれる友達がいて、本当に嬉しかったのを覚えています。この時、「時間がかかっても、見た目が不格好でも、懸命に頑張ってさえいれば、きっと理解してくれる人はいる」——そんな確信に似た自信を初めて持てたような気がしています。
その後、解析学への興味が高まり、一時は数学の研究者になりたいという夢を抱き院を目指して勉強したこともありました。しかし卒業間近、担当教授から「研究者になるのは難しいかもしれない」と告げられました。就職活動もほとんどしていなかった私でしたが、その教授の紹介で測定器の製造メーカーに就職することができました。

障がいが有るとか無いとか関係なかった。
伊豆踊り子号が下を走る歩道橋を渡ると、小さな会社が並ぶ街並みが広がります。その一角にあった4階建ての白い建物が、私が27年間働いた測定器メーカーでした。
入社した当時は、測定器の制御がアナログからデジタルへと移行する時期でした。私のチームには、マイクロコンピュータを用いて測定器を制御するプログラムを作成するという課題が与えられました。測定したデータを物理量に変換し、表示・印刷・パソコンとの通信までを管理するという内容です。
手に麻痺があり、コーディングには時間がかかりましたが、アルゴリズムを考えることに多くの時間を費やしたため、大きな支障にはなりませんでした。
何より、チームの皆さんが私を自然に受け入れてくれたことに、今でも感謝しています。言葉が聞き取れない時は何度も聞き直してくれたり、細かい配線などもサポートしてくれました。
「高機能な測定器を作りたい」「使いやすい製品にしたい」——そんな想いに溢れたチームには、障がいの有無は関係ありませんでした。ただ「良い製品を作ろう」という情熱があっただけです。
怪我により通勤が難しくなるまで、私は皆さんの助けをいただきながら、27年間勤め続けることができました。この時間は、かけがえのない宝物です。
まとめ
「もうダメだ、立ち直れない」と思ったことが何度あったことか。その度、家族や友人をはじめとする周囲の人達の暖かい理解と支援に支えられてきました。一人では辿り着けない道でした。家族をはじめ周囲の人達に、心から感謝しています。
